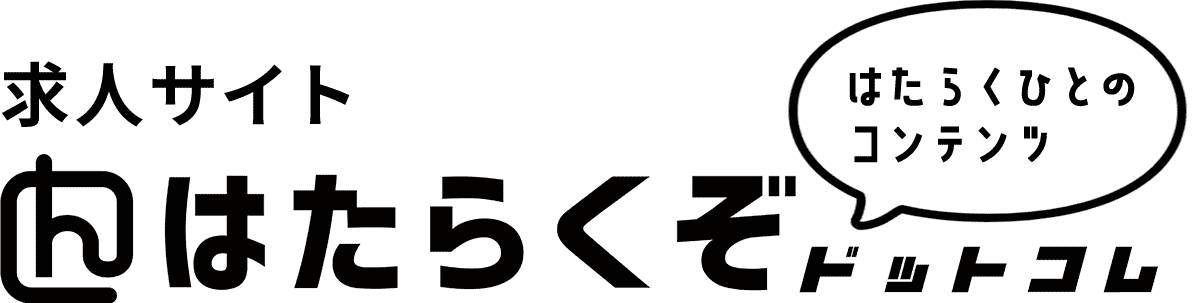「公務員=安定」というイメージが強く、今や小学生にも人気の高い職業である公務員。しかし「公的機関」にもさまざまな機関や部署があり、実際の仕事内容や魅力は案外知られていません。
この記事では、国家公務員や地方公務員など、公的機関の事務職のリアルな仕事内容や魅力、向いている人などを紹介します。社会の基盤を支える役割と、キャリアの選択肢について考えていきましょう。
公的機関の事務職とは?仕事内容を紹介
公的機関で働く事務職の主な仕事内容を紹介します。
公的機関とは?
そもそも公的機関とは、公共のために業務を行う機関を指します。具体的には国会、裁判所、中央省庁(官公庁)、地方公共団体(都道府県や市町村の役所)、独立行政法人、日本銀行などがあります。
国民や住民のために、社会生活の維持や福祉向上など公共的な目的を担うのが公的機関の目的です。
公的機関:事務職の仕事内容
公的機関の事務職は、一般的に行政職や事務系公務員と呼ばれる職種です。業務内容は多岐にわたりますが、主な仕事内容を紹介します。
窓口・対人業務
行政と住民をつなぐ「顔」として、行政サービスを提供する窓口の役割を担います。
例えば、役所の窓口では住民票や戸籍などの届出、マイナンバーカードの交付手続き、印鑑登録などといった、住民生活に欠かせない手続きの受付や審査、交付を行います。
また税金(固定資産税、住民税など)や社会保険(国民健康保険、国民年金など)に関する申請や相談に対応し、必要な書類を案内したり、計算処理をしたりします。
相談・案内業務
障害者や生活困窮者向けの福祉制度、子育て支援サービス、高齢者向けの介護サービスなど、広範囲にわたる行政サービスを提供します。窓口や電話での問合せや相談に専門的な知識で対応し、相談者が適切なサービスを受けられるよう案内します。
政策・事業の企画
地域の経済状況や環境問題、防災対策、教育水準など、各分野に関するデータを分析し、新たな課題解決策や地域振興策を検討・立案します。
例えば新しい公園の整備計画や、観光振興のイベント企画、地域ボランティア活動の支援策など、行政として住民のために行うべき政策や事業を設計します。
内部管理・事務処理
公的機関も1つの組織である以上、組織運営を支えるバックオフィス業務が不可欠です。公的機関の事務職では、公的機関の内部管理や事務処理をする業務もあります。
公文書の作成・管理や、職員の人事管理や給与、福利厚生に関わる業務、公共事業費や運営費などの支払い処理や収入管理、決算書の作成などを行う会計・経理事務など、幅広い業務があります。
公的機関の事務職のキャリア形成

公的機関の事務職は、一般的に数年ごとの部署異動をしながら、各部署を経験していきます。特定分野の専門知識のみならず、地域社会全体を俯瞰して運営できるため、総合的なスキルが身についていきます。
福祉や税務、都市計画、環境など、多岐にわたる分野があり、異動のたびに新しく覚えることもありますが、一般企業では携われない社会の基幹部で仕事をするやりがいがあります。
総合的な視野を養い「行政のプロフェッショナル」として幅広いキャリア形成ができるでしょう。
公的機関で培った総合的なスキルと、高い法令遵守意識、組織調整力、正確な文書作成能力は、民間企業の総務部や企画職、コンプライアンス部門などでも高く評価されます。
公的機関の事務職の魅力とやりがい
公的機関の事務職として働く魅力とやりがいについて紹介します。
社会への貢献度が高い
一般企業であれば利益を追求することはマストですが、公的機関では住民全体の利益と公共の福祉を目的としています。自分の業務が人々の生活や地域社会の発展にダイレクトにつながる、スケールの大きなやりがいがあります。
誰もが安心して暮らせる社会の基盤を支えているという、社会的貢献度の高い仕事といえるでしょう。
雇用の安定と充実した待遇
公的機関で働くことは、安定した収入が期待できます。景気に左右されることなく、長期的なキャリアプランも立てやすいでしょう。
また福利厚生も充実しており、休暇や育児・介護休業制度など、ライフイベントにも合わせた働き方がしやすいのも魅力です。
多様な経験で成長できる
異動を通じて、一般企業では叶わないような多種多様な業務に携わることができます。土木、福祉、教育、環境、都市整備など、さまざまな経験ができるため、成長機会に恵まれます。
入職後の研修制度も充実しており、継続的なスキルアップのサポートを受けられる環境もあります。
公的機関の事務職に向いている人とは?
協調性がある
公的機関の仕事はチームで行うことがほとんど。個人の成果を求められるより、組織全体として最適な結果を出すことを優先します。チームワークを乱さずチームの一員としての協調性が求められます。
派手な仕事より、地道な書類整理やデータチェックも多いですが、ミスなく正確に作業を継続できる根気強さも必要です。
常に学び続ける意欲がある
ひとつの部署に長く居続けることはほとんどなく、異動があることが前提です。新しい部署にいくたびに、新しいことを覚える必要があるため、常に学び続ける意欲がある人には向いているでしょう。
広く多くのことを知りたい、学びたいと思う人には適しています。
ストレスを適切に処理できる
公的機関の事務職で、特に窓口業務に携わると、時に住民からの厳しい指摘を直接受けることもあります。また異動により慣れない業務でプレッシャーを受けることもあるでしょう。
このようなストレスに直面しても感情を適切にコントロールし、冷静に業務に取り組める人は公的機関で成果を出すことができます。
公的機関の事務職になるには?主なルートを紹介

基本的に公的機関の事務職は「公務員」として採用されます。公務員には大きく分けて「国家公務員」と「地方公務員」があるので紹介します。
国家公務員
国家公務員は、各省庁(中央省庁)、裁判所、国会などで働き、国の政策立案や運営に関わります。
【主な試験の種類】
- 総合職: 政策の企画立案など、高度な知識・判断力を必要とする業務に従事します。人事院が統一して試験を実施します(裁判所職員などは別途実施)。
- 一般職: 政策の実施や、定型的な事務に従事します。
- 専門職: 国税専門官、労働基準監督官、外務省専門職員など、特定の分野の専門知識を必要とする業務に従事します。
地方公務員
採用される職種は「行政事務」「一般事務」などと呼ばれることが一般的です。各都道府県、各市区町村が独自に実施します。
- 上級(大卒程度): 大学卒業程度の学力レベル。キャリアの中核を担う職員として採用されます。
- 中級(短大卒程度) / 初級(高卒程度): 短大・高校卒業程度の学力レベル。
- 社会人経験者採用枠(中途採用): 民間企業での職務経験を持つ人を対象とした選考。年齢制限が緩和され、筆記試験に加えて職務経験論文や面接が重視される傾向があります。
まとめ
公的機関の事務職は、単に安定している職業というだけでなく「社会貢献」という大きなやりがいと、異動による「多様な成長機会」に恵まれた仕事です。
自分の仕事を通じて人々の生活を支えたい、長期的に安定した環境で市場価値の高いスキルを身につけたいと考える人は、ぜひ公的機関の事務職へ挑戦してみましょう。